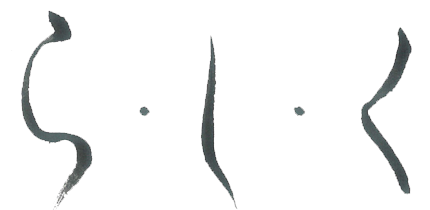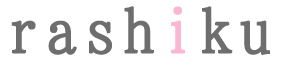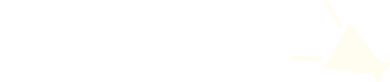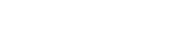自分らしく
愛は罪を贖えるか? 容疑者Xの献身

原作のミステリー小説は直木賞もとり、TVドラマや映画化もされたほど有名なものらしいが、私はまったくこれらを知らず、今回、舞台で初めてこの物語に触れた。厄病神のような前夫を殺めてしまった薄幸の母子を、密かに彼女らを愛している隣人の天才数学者、ただし、世間的には埋もれてしまっている冴えない男が、自らがその罪を被ることで守ろうとする。
そのためにあらゆる策略を張り巡らし、まんまと警察を欺き、そしてことの真実を突き止めようとする。「かつての友人、やはり天才的な物理学者、ガリレオとの知恵比べ」というのがプロットで、トリックが意外性に富み緻密なだけに、さまざまな伏線が複雑に絡み合って物語となる。演出・脚本の成井豊はそれらをスッキリとコンパクトにまとめ、畳みかけるようなスピードとリズム感で舞台を構成した。
数学者は母子が警察に虚偽証言をしなくてすむように、そして何より罪悪感に捕らわれないような工作までも、母子にさえ知らせぬままに行うのだが、最終段階で思わぬ破たんが起きてしまう。他人に罪を被せ、自分たちが幸せを得るという重荷に耐えきれぬ娘が自殺未遂、その結果、母親が真相を警察に自白してしまうのだ。
舞台では、演出のスピード感に幻惑されて見過ごされやすいが、実は結末には救いがない。希望を失い自殺さえ企てていた数学者は、等身大の自分では決して実現できないであろう愛する人々の幸せを、殺人を千載一遇のチャンスとして叶えることで、心置きなく残る生涯を数学だけに捧げて生きようとしていたのである。
だが、母が服役したら、傷ついた娘はどうなるか? 何よりも自分が唯一頼りとしていた知の自負心が打ち砕かれては、いくら母が「あなたと一緒に罪を償います」と言ったところで、それは地獄の道行きでしかないだろう。
帰途は荒川の堤防を夜風に吹かれながら歩いて帰った。コロナ禍の東京だが、街の灯りは思ったよりは暗くはない。人は生きていかなければならないからだ。生に反する人の行いを罪と呼ぶならば、そして、生に欠かせぬ人の心の営みを愛と呼ぶならば、コロナは愛と罪が誰にとっても隣り合わせで、矛盾でさえないことを改めて認識させた。緊急事態宣言下の観劇が、わずかでも自分の、そして他人の感染リスクを高める罪だったことは間違いない。そして、一年以上延期されたという舞台にかけた役者たちへのステージへの愛は、そして僕たちの生きる喜びへの愛は、その罪を贖うことができるだろうか?
サポーター

- いよいよ還暦、そして定年。「この機会に生き方をガラッと変えられないか?」などとずっと考えています。ごく「フツー」の冴えないサラリーマン生活だったわりには、なぜかちょっとした冒険にもいろいろとした巡り合えたし、ここまで生きてこられた恩を自分以外に返さなきゃなぁ、と思う今日このころ。
プロフィール
最新の記事
 自分らしく2025年8月15日永遠の愛のソネット~あなたを愛してしまう
自分らしく2025年8月15日永遠の愛のソネット~あなたを愛してしまう 自分らしく2025年6月15日黒鳥の歌が聞こえない~What A Wonderful World
自分らしく2025年6月15日黒鳥の歌が聞こえない~What A Wonderful World 自分らしく2025年1月6日天国に一番近いのに見過ごされてきた島
自分らしく2025年1月6日天国に一番近いのに見過ごされてきた島 自分らしく2024年10月15日空が一面に海に見えた日
自分らしく2024年10月15日空が一面に海に見えた日