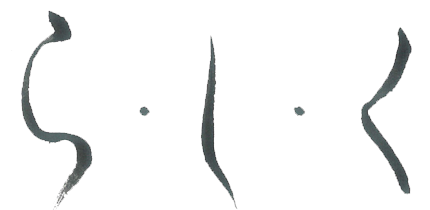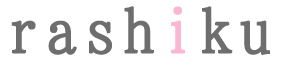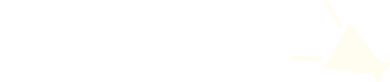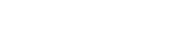自分らしく
【Book】〈いのち〉とがん〜患者となって考えたこと〜

病気になって感じたこと、考えたこと。突然の膵臓がん宣告に…
著書の坂井さんは1960年に生まれ、NHKのディクレター、プロデューサーとして医療の番組にも関わっていました。本書は2016年に発症した膵臓がんについて、著者自身が2年後から記録としてまとめたものです。「病気になった自分」と「伝える仕事をしてきた自分」の接点で、いまなし得ることをしてみるべきとの思いで、「自分の気持ちの杖であり、誰かの気持ちのどこかに届けばうれしい」と書き始めたそうです。
治療は2016年の手術から始まります。膵頭十二指腸切除により、なんと、膵頭部、胃の一部、十二指腸全部、胆のう全部、胆管の一部、リンパ節を切除。包帯でぐるぐる巻きになった「瀕死のミイラ」状態でICUから戻った術後は、激しい後遺症に悩まされることに。激しい下痢と脱水での再入院と、がん再発による抗がん剤治療、再手術、再再発、再度の抗がん剤治療…まさに「容赦なき膵臓がん」と一緒に過ごしました。ここで坂井さんのすごいところは、がんの攻撃に対して「闘争心というより人生に対する欲望が芽生えた」と言ってしまうことです。
「学ぶ患者」としての好奇心
坂井さんは『ランセット』という雑誌が医学の世界で大きな権威をもつことを知っていて、論文を読んでいたとのこと。それが驚きでした。その『ランセット』で発表された効果のあるTS-1という薬を使うことになるのですが、「医療の進歩を信じろ」という先輩の言葉に背中を押されて治療をスタートされます。
自分の治療方法に好奇心を掻き立てられるものの、退院時期にも「腸瘻」という管が抜けずに栄養剤を送り込んでいました。激しい下痢が止まらないなか、抗がん剤治療が始まりましたが、半年後には活字を読む気力が戻り、論文や医学書などを読み始めるのです。そして、抗がん剤治療スケジュールや副作用のこと、また副作用をことさら強調して伝えるマスコミの責任の重さ、『がんと闘うな』の著者である近藤誠医師が与える影響の大きさなどを、極めて冷静に分析しています。
患者の「心を支える」仕組み
厳しい化学療法の副作用に耐えながら、いわゆる闘病ブログや闘病記などを読みますが、「心を支えることにピンとくるものはなかった」と言っています。つまり、「乗り越えるためのヒントがない」ということです。私自身の病気とは比べようもありませんが、著者と同じ気持ちだった時期もありました。
そこから、患者の意識調査が少ないことに驚き、静岡がんセンターが実施した調査に行きつきます。しかし、患者の要望の1位は「自身の努力」。ここから、「もっていく場がないのでは?」と読み解き、「がん医療のなかには、緩和ケア、精神腫瘍科、精神科、心療内科、がん哲学外来などがあるが、自分がどこに行けばわからない」と言っています。そして「何でも主治医から、というのはもうやめたほうがいいのでは?」とも。確かにがん患者の9割はうつ病・抑うつになるとも言われていて、「実際に自分がどこに行けばよいのか?」と悩んでいる方はとても多いと実感しています。
坂井さんは、同じ高校の同期でした。2018年11月に天国に召された、その直前までこの本を執筆されていたことを知り、驚きました。お別れ会に参列し、すべて生前に自分で企画したものと聞いて、涙が止まりませんでした。私のなかで坂井さんの記憶は、「体育会の応援団でチームを盛り上げていた明るく元気で笑顔の魅力的な女子高生」で止まっています。この2年間、彼女が苦しみながらもきちんと伝えたかったことを、こうして本を通して受け取る機会をくれたのだと思います。
〈いのち〉とがん〜患者となって考えたこと〜
著者:坂井律子
出版社:岩波書店
▼岩波書店
https://www.iwanami.co.jp/book/b432946.html
サポーター

最新の記事
 自分らしく2020年4月29日【Book】〈いのち〉とがん〜患者となって考えたこと〜
自分らしく2020年4月29日【Book】〈いのち〉とがん〜患者となって考えたこと〜